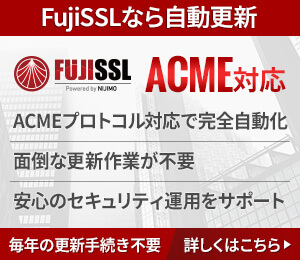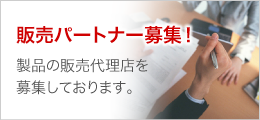2026年3月15日より、SSL/TLS証明書の有効期間が現行の398日から200日へと短縮されます。さらに段階的に、2027年には100日、2029年には47日まで短縮されることが決まっています。
この変更は、セキュリティ強化と将来的な耐量子暗号への対応を目的とした業界全体の取り組みです。証明書管理を従来のように手作業で行うことは現実的ではなくなり、今後は自動化の導入が不可欠となります。
Contents
200日への短縮が意味すること
200日という期間は、これまでの有効期間のほぼ半分です。証明書の発行・更新・展開を従来のペースで続けていては、期限切れによるサービス停止やセキュリティリスクを避けることが難しくなります。
さらに業界では、最終的に47日間まで短縮することがすでに決定しています。今回の200日化はその第一段階であり、今後の運用体制を整えるための重要な準備期間といえます。
有効期間短縮の背景
長期間の証明書は、潜在的なリスクを抱えています。その要因は以下の通りです。
- 組織や担当者の変更
- 担当者の異動や退職により、管理が不十分になるリスクがあります。
- ドメイン所有者の移転
- 所有権が変わっても古い証明書が残り続ける場合があります。
- サイバー攻撃の進化
- 攻撃手法が高度化する中で、長期間利用される証明書は脆弱になりやすいです。
こうした背景から、有効期間を短縮することには次のような効果があります。
- リスクの最小化
- 脆弱性を長期間放置する可能性を減らせます。
- セキュリティ検証の頻度向上
- 更新サイクルが短くなることで、最新のセキュリティ基準を適用しやすくなります。
- 新技術導入の促進
- 自動化や暗号化技術の導入を後押しします。
手作業管理の限界と自動化の必要性
47日間まで短縮されると、証明書の更新は年間7〜8回以上必要になります。これはすでに人手で管理できる範囲を超えており、自動化なしでは運用が成り立ちません。
手作業管理を続けることで生じるリスク
・証明書の期限切れによるサービス停止
有効期限切れにより、サイトやサービスが突然停止する危険があります。
・ブラウザ警告による顧客信頼の失墜
セキュリティ警告はユーザーの離脱を招き、ブランドの信頼性を大きく損ないます。
自動化によって得られる効果
・正確で迅速な更新
更新忘れやヒューマンエラーを防止できます。
・ライフサイクルの一元管理
FujiSSLではすべての証明書を一括で把握・管理可能です。
・運用負担の軽減
担当者の作業時間を大幅に削減し、運用コストを下げます。
ポスト量子時代を見据えた対応
証明書ライフサイクルの自動化には、「暗号技術の俊敏性(Crypto Agility)」を確保できるという重要な意味もあります。耐量子暗号が必要になった際、自動化基盤があればキーやアルゴリズムの切り替えを迅速に行うことができます。
FujiSSLは、この自動化基盤を整えているため、新しい暗号方式への移行も滞りなく実現できます。将来の技術変化に備え、証明書運用を中断させることなく継続できる点が大きな安心につながります。
いま取り組むべきこと
2026年3月15日以降の200日化、さらに将来の47日化に対応するために、組織は次のステップを踏む必要があります。
- 証明書の洗い出し
- 利用中のすべての証明書を把握し、一覧化する。
- 依存システムの把握
- ロードバランサー、VPN、コンテナなど、証明書が利用される環境を特定する。
- 自動化の導入計画
- REST APIやACMEを活用して、証明書の発行・更新を自動化する。
まとめ
SSL/TLS証明書の有効期間短縮は、業界全体で進められているセキュリティ強化の一環です。2026年3月15日の200日化を皮切りに、2029年には47日というこれまでにない短い有効期間が標準となります。
この変化に対応するためには、証明書ライフサイクルの自動化が不可欠です。今のうちに体制を整え、変化をリスクではなく競争力強化の機会として活かしていくことが求められています。
FujiSSLの取り組み
FujiSSLでは、ACMEやREST APIを活用した自動更新機能を提供し、複雑な証明書管理をシンプルに運用できます。さらに、将来の耐量子暗号(ポスト量子暗号)への移行にも備えています。お客様が安心してインターネットサービスを運用できるよう、最新のセキュリティ基準と運用体制を提供し続けます。
SSL/TLS証明書の自動化や運用改善について詳しく知りたい方は、こちらからお問い合わせください。